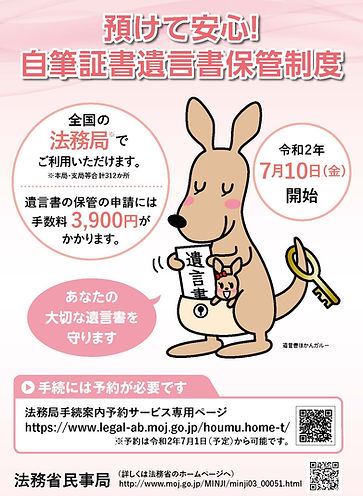よこすか司法書士事務所
Yokosuka Solicitor's Office
相続手続、遺言や生前贈与、遺産分割についてのお悩み・ご相談は、当事務所へお気軽にお声掛けください。
全国対応致します。
0285-27-7997
相続登記申請の義務化について
相続登記の申請が義務化されました。
(2024年4月1日より)
これはいわゆる「空き家問題」の全国的な拡大の解消のための施策となります。
1.相続登記の義務化とは?
相続によって不動産を取得した人(具体的には、遺言による場合、遺産分割協議の成立など)が
相続によって所有権を取得したことを知った日
または
遺産分割協議が成立した日から3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません。
相続登記を行わない場合、「10万円以下の過料」
が科されることがあります。
しかし、家族や兄弟の間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらないため、登記ができないようなケースが当然考えられます。
「そんな場合でも、罰金は払わなければならないの?」
と心配している方に向けた救済措置があります。
それが、「相続人申告登記」です。
2.相続人申告登記とは?
上記のような事情により、すぐには登記申請はできないが暫定的に
「登記簿上の所有者について相続が開始したこと」と
「自分がその相続人であることを申し出る」制度が定められました。
たとえば相続人がABCの3人存在する場合に、
Aさんだけがひとりで相続人申告登記を行った場合には
過料を払う義務がAさんは免除されます。
(※BさんCさんは過料を払う義務は免除されません)
この申出がされると、登記簿に申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます。(※持分までは登記されません。)
ただし、これは完全な権利の取得を公示するものではありません。
土地を売却するなどが必要な場合には、正式な相続登記を行う必要があります。
3、相続人申告登記は、何のため?
相続人申告登記によって、国による相続財産の把握や処分が円滑に進む事が期待されています。
申告登記が一人からでも行われれば、少なくともこの不動産には相続が発生しているという事実が公示されて国や自治体や他の当事者もその事実を知る事ができます。
その結果、例えばその不動産を取得したいと希望しているひとが、その登記簿を手掛かりに相続人に連絡を入れるなどにより、相続手続の推進がなされる可能性が期待できるのです。
※具体的な手続については当事務所にご相談ください。